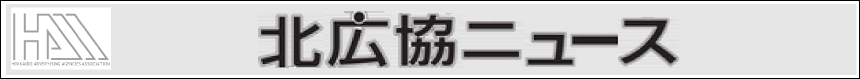『明日へのベクトル(連載118)』
「ポスト真実」の時代に、求められる知恵。
マーケティングプランナー 臼井 栄三
ポスト真実(post-truth)という言葉を耳にしたことはあるだろうか。客観的な事実よりも、感情に訴える方が強い影響力を持つ状況を指す。インターネットやAIなどのITが進展する中で、「ポスト真実」の様相はますます濃くなっている。
2024年は、ポスト真実が私たちの地域や仕事にも強く関係していることを実感した年だった。こう書けば、アメリカ大統領選や日本での首長選などを連想した人もいるだろう。真偽不明の情報が多くの人の感情を刺激し、広く拡散されていくのを目の当たりにした。
選挙ばかりではない。今年、僕が衝撃を受けたのは徳島大学発のベンチャー企業「グリラス」の破産だった。食用コオロギの生産や商品開発を手がけ、「徳島から世界の食糧危機に挑む」と各方面から注目され、期待もされていた。
2020年に、グリラスは無印良品へコオロギパウダーの提供を開始。「コオロギせんべい」がヒットするなど、業績は順調なように見えた。しかし2022年11月、徳島県立高校の生徒にコオロギパウダーを使った給食を提供したことから、雲行きは急変する。
ネット上で実にさまざまな情報が広がっていった。その中にはとんでもない誤りやデマも多かったし、悪意に満ちた声もあった。SNSは投稿すると、その先のコントロールが利かない。やがて陰謀論と結びつき、国はコオロギの食糧で人口削減計画を進めているといった話にまで広がっていった。
グリラスの悲劇は、遠い世界の話ではない。私たちは広告主のパートナーとして毎日仕事をしている。広告主が似たような状況に置かれたら、私たちは何ができるのだろうか。ポスト真実の時代、私たちの知恵と実行力が求められている。
マーケティングプランナー
臼井 栄三

株式会社DGコミュニケーションズ 佐藤 優次
「広告業界におけるテクノロジーと人間味のバランス」
急速なテクノロジーの進化に伴い、広告業界も変革の時を迎えています。ビッグデータを活用したターゲティングやAIによるクリエイティブ生成、さらにリアルタイムでの分析・最適化といった高度な技術が導入され、効率的かつ正確なアプローチが可能になっています。しかし、私たちが見落としてはならないのは、これらのテクノロジーによる利便性が「人の心に響く広告」を生み出すための唯一の手段ではないということです。データが導き出す数値の奥にある、言葉にしにくい「人間らしさ」をどう広告に反映させるかが、これからの広告制作においてますます重要な課題になっています。
人々の心に残る広告には、単なる数値や分析結果だけでは表現できない温かみや共感、時には思いがけない驚きが含まれています。データから得られる「ターゲット層の傾向」や「消費行動のパターン」はもちろん有用ですが、それだけでは本当の意味での感動や共感にはつながりにくいのが現実です。そこで必要となるのが、クリエイティブに携わる人々のインサイトや、人間が本能的に持つ「共感」の力です。この「人間味」は、AIが生み出す効率的なクリエイティブにはなかなか置き換えられない部分であり、広告業界が持ち続けるべき独自の価値だと考えます。
私たちの広告制作現場では、ターゲット層のインサイトをさらに深掘りするためのワークショップや、プロトタイプの制作段階から消費者の意見を積極的に取り入れる取り組みを行っています。具体的には、ターゲット層の感性やライフスタイルを理解するために、データに基づいた仮説だけでなく、実際の消費者と対話することで得られる生の意見や感情を反映させる方法です。これにより、単に効率よく届くだけでなく、見る人に「自分ごと」として共感される広告を目指しています。また、AIが導き出したパターンや予測データに対しても、クリエイターの感性や独自の視点を加えることで、効率化とともに「驚き」や「気づき」を提供できるクリエイティブが生まれるのです。
テクノロジーは日々進化し続け、広告業界における影響力も増していますが、これをうまく活用しつつも、広告に不可欠な「人間味」をいかに保っていけるかが、これからのクリエイティブにおける最も重要な課題だといえます。単なる情報提供を超えて、見る人の心に響き、記憶に残る「物語」をどう作っていくのか。テクノロジーとクリエイティビティの絶妙なバランスが、その答えになるのではないでしょうか。